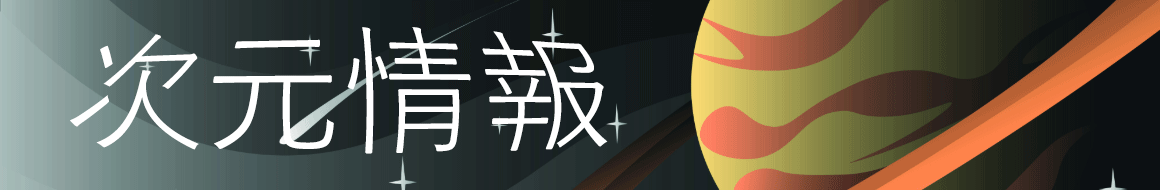悲しみの最奥の光と静寂の情景~中原中也『一つのメルヘン~』
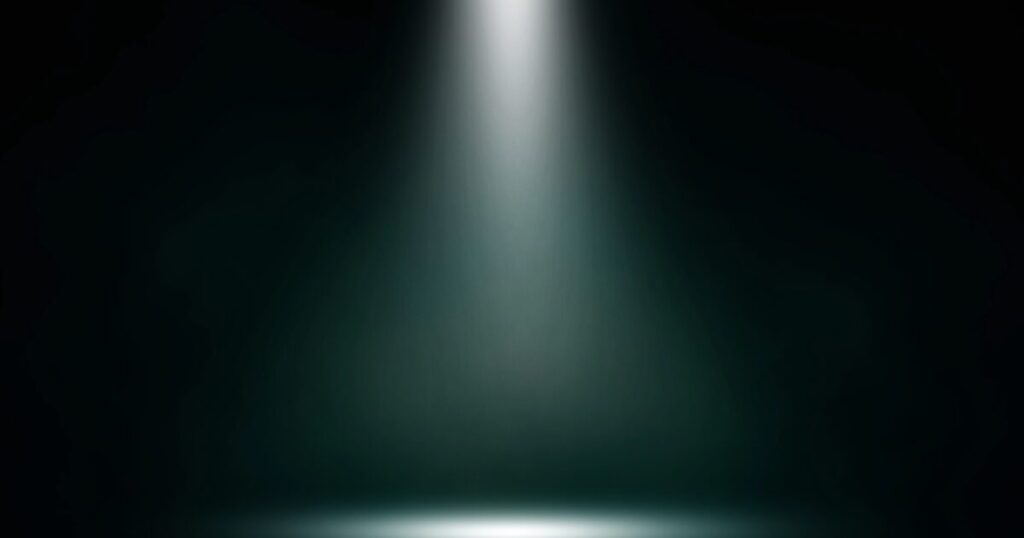
中原中也『一つのメルヘン』
秋の夜は、はるかの彼方(かなた)に、
小石ばかりの、河原があつて、
それに陽は、さらさらと
さらさらと射してゐるのでありました。陽といつても、まるで硅石(けいせき)か何かのやうで、
非常な個体の粉末のやうで、
さればこそ、さらさらと
かすかな音を立ててもゐるのでした。さて小石の上に、今しも一つの蝶がとまり、
淡い、それでゐてくつきりとした
影を落としてゐるのでした。やがてその蝶がみえなくなると、いつのまにか、
今迄流れてもゐなかつた川床に、水は
さらさらと、さらさらと流れてゐるのでありました……
国語の授業で習った忘れ得ない作品というものが誰しもあるかと思います。
中原中也の『一つのメルヘン』は、知識経験が浅い高校生だった頃の私にも、
美しさ、悲しさ、静謐で心を震わせました。
「この詩はとんでもない世界を描いている。」
この詩を読んだ感想を表現できるだけの語彙力は、
当時の私にはまだなかったけれど、そのことだけは分かりました。
時を経て、今だから分かります。
この詩が湛えているのは、人の感性が到達しうる果て無き頂点から差し込む「光」である、と。
『一つのメルヘン』は「みたましずめ」
この作品は、息子の死で詩人自身が絶望の深淵を彷徨い、
行き着いた情景を描いていると感じます。
中原中也が行き着いた情景は、地獄の様相だったでしょうか。
絶望の淵は、音をたてて小石に降り注ぐ美しい光でほのかに照らされた河原と、
光が降り注ぐ音が聞こえてくる静寂に包まれた聖域でした。
蝶は亡き息子の生まれ変わり。
生命を表す川の水は「生きよ」と伝え、
詩人に命を吹き込む。
この聖域を感得した詩人自身は救済されたことでしょう。
そして、悲しみと苦悩の中にいる後世の読者にとっても救済です。
この世は、
本当は美しい。
一つのメルヘンは、また、常世を思わせます。
常世とは
常世(とこよ)、かくりよ(隠世、幽世)とは、永久に変わらない神域。死後の世界でもあり、黄泉もそこにあるとされる。「永久」を意味し、古くは「常夜」とも表記した。日本神話や古神道や神道の重要な二律する世界観の一方であり、対義語として「現世(うつしよ)」がある。「常夜」と記した場合は、常に夜の世界であり、常夜という表記の意味から、死者の国や黄泉の国とも同一視される場合もある。ただし、折口信夫の論文『妣が国へ・常世へ』(1920年に発表)以降、特に「常世」と言った場合、海の彼方・または海中にあるとされる理想郷であり、マレビトの来訪によって富や知識、命や長寿や不老不死がもたらされる『異郷』であると定義されている。
古神道などでは、神籬(ひもろぎ)・磐座(いわくら)などの「場の様相」の変わる山海や森林や河川や大木・巨岩の先にある現実世界と異なる世界や神域をいう。
出典:常世-Wikipedia
常世の解説から分かるように、河原は現実世界と異なる神域なのですね。
「常夜」と記された場合、常に夜の世界である死者の世界とされ、
この作品が秋の夜が舞台であることと重なります。
詩人の亡き息子がいる常世に魂を飛翔させて見てきた世界。
その世界を言霊で表現したレクイエムである『一つのメルヘン』は、
日本文学が誇る至宝です。
今の私は、この詩を授業で扱うとしたらどう伝えるだろう。