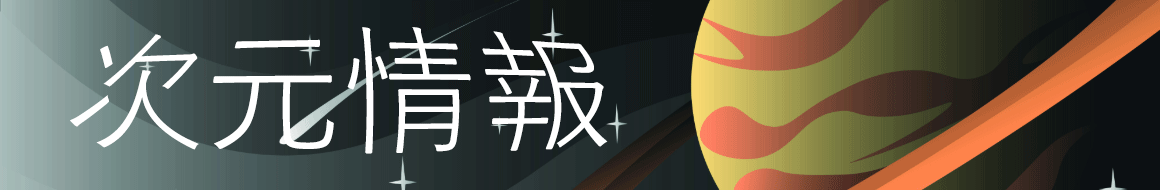今際の際からの生還

今回は、2019年3月の父が脳出血に見舞われた時の実際の様子と不思議な出来事を振り返り、物語風に記しました。
「爺さんが大変かもしれない。」
「もしかしたら痴呆症になってしまったかも。」
桜がほころびはじめた花冷えの3月末、母・佳久子から電話がかかってきた。父・晴道は、前日から「携帯の文字をどう打てば良いかわからない。」「お風呂のボタンを押そうするけれど、何がどうなっているのかわからない。」と、今までできたことが急にできなくなったと言う。
それでも春道は、仕事に出かけたというのだ。60歳で定年になった後も20年以上働き続けてきた春道は体力に自信があった。10代から続けている野球をスーパーシニアとして今でも続けている。
しかし明らかに体の中で重大なことが起きていると心配した佳久子は後をつけたが、病院で診察を受けるよう説得できず、娘・常世に電話をかけたのである。
常世は「痴呆症はそんなに急に発症するものではないと聞いたよ。病気だよ。病院に連れていかないと!」と伝えた。すぐに晴道の元へ向かうため、バスと電車を乗り継ぎ母親との待ち合わせの場所へと向かった。
夕方の車窓を流れる景色は、薄墨色の雲が重く垂れみ、季節はずれの寒さが肌をなでた。佳久子と常世は駅で待ち合わせし、タクシーで春道のいる職場へ急行した。
職場は、東京郊外の某国際機関で、春道は警備の仕事をしていた。受付の窓口の同僚警備員に、春道の家での様子を伝え、心配で職場に来たことを伝えた。同僚警備員は、いつもと違う様子の春道に配慮し、休ませてくれていて休憩室にいると教えてくれた。
休憩室に向かうと、じっと一点をみつめ座っている春道がいた。常世は、土気色で目が小さく落ち窪んで生気がなく、黒い雰囲気がまとわりついている春道を見た。春道の体が大変なことになっていることを直観し、今すぐかかりつけの病院での受診を説得した。
春道は立ち上がって歩けるには歩けるが、柱にぶつかりそうになったりするので急いでタクシーで病院に向かった。地域の人たちに信頼されている温かな人柄の町医者が心配そうに出迎えてくれた。「せん妄」と診断され、脳神経外科にかかることを強く勧められ、紹介された病院へ再びタクシーで移動した。
すでに夜の8時近くになっていた。静かな院内で、佳久子と常世はMRI検査の結果を待っていた。呼ばれて処置室に入ると、春道はベッドに寝ていて意識ははっきりしている様子だった。特に痛がったり、苦しがったりせず落ち着いていた。MRIの画像を見ると、脳の左真ん中部分に白い影があった。
脳出血である。
脳神経外科の専門医がいる病院を紹介され、救急車で移動。到着後2時間ほど検査しただろうか、すでに日付が変わろうとしていた。結果は、脳出血による視野狭窄の後遺症が残ること、長年仕事、運動と動いてきたからか、腎臓も弱っており、持病の肺気腫もかなり進行しているのだった。
まさに満身創痍で、それでも春道は気丈に振舞う。医師の対処、処方された薬が効いたらしく、次第に回復に向かっていった。だいぶ落ち着いた頃、春道が「右目の端に黒い影が見えていたけれどいなくなった。」と言った。
大事には至らず10日で退院し、自宅に戻って、高血圧抑制ための薬で体調を管理しながらゆっくりと過ごした。血圧は徐々に正常値に近づき、容体は安定した。
しかし、脳出血で体力が低下した春道の体を、今度は、持病の肺気腫が畳みかけるように悪化し、襲った。少し歩いては、息苦しさで立ち止まらずにはいられない日が続くようになった。
息苦しさが数日続き、春道が昼寝していると、突然呼吸困難に陥った。佳久子が救急車を呼ぼうとするが、春道は呼ばなくていい、大丈夫だと制止する。しかし佳久子は急いで救急車を呼ぶ。程なくして救急車が到着。隊員から「危険な状態だ。」と告げられた。
佳久子から春道の容体が悪化したと連絡があり、常世は病院に向かった。
病院に到着し、佳久子と常世の弟・圭と会い、病室に向かった。春道は、熱で顔が赤くなり酸素マスクをしていた。肺炎を発症したのだった。
「次から次へといろいろ起きるよ。」と、春道は心配させないように明るく言う。
この日、春道は1人で近くの公園のベンチに座り、近所の老婦人に話しかけ世間話をしたらしかった。普段の春道は自分から話しかけることはないのに、珍しいことをして気になった、と待合室で佳久子が話すのだった。その数時間後、容体が急変し再入院したのだ。
人によっては、今際の際において、まるで予期するような、不可思議な様子を見せると言われている。
手の甲をじっと見つめる(右手鏡)
故人を見る
黒い影を見る
普段であったら絶対しないことをする
生きたい気持ちを強くもって、押し寄せる病を乗り越えようと前向きな春道は、幸いにも肺炎の症状は落ち着いていった。
それでも持病の肺気腫のため余談は許さない状況で、病室で寝ていると、誰かに背中を押される、と言う。救急車を待っている間の記憶が全くなく、真っ暗闇の中で「あちら」に行けば楽になれると思ったと話すのだった。
今際の際を行きつ戻りつする春道が語る言葉を聞くたび、父親とつながる「何か」が失われていく恐ろしさと嘆きが、常世の力を深く深く削ぐのを感じた。
その後、一度失った肺の機能は戻らず酸素ボンベを持ち歩くことになったが、穏やかに生活できるまでになった。
100歳まで生きる、と春道は言うのだった。